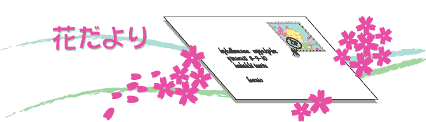
「んむう〜。」
レオリオは机の前で唸った。目の前には白い便せんと封筒。宛名はとっくにかいてある。今、どこにいるかわからない恋人の名前だ。
「いざ改まると難しいもんだよ。」
がしがしと短い黒髪をかきむしると、レオリオはまたペンをとった。
『拝啓
クラピカ、元気か。オレも元気だ。』
「あ〜っと、違う、季節の挨拶ってーのを書くんだったか。」
レオリオはクシャクシャと便せんを丸めて捨て、新しい一枚をひろげた。
『拝啓』
そのままレオリオはしばらく固まった。拝啓、のあとがでてこない。季節の挨拶といわれても、なにをどうかいていいのやら。
「まったく、しちめんどくせぇ決まりが多いぜ、ハンゾーの国ってのは。」
☆☆☆☆☆☆
手紙を書くなど、柄にもない事を始めたのはほんの気紛れだった。
恋人の誕生日がくるのに一緒にすごせないとボヤくレオリオに、東の国からきた留学生が言ったのだ。
「手紙を書いたらどうですか?」
レオリオは苦笑した。手紙を届ける事ができるならまだ悩みはしない。
「仕事の都合でな、どこにいるかわかんねぇんだ。移動してるだろうしなぁ。」
まぁ、愛のメールは毎晩送ってるけどな、と臆面もなくいう男に、物腰の柔らかな留学生は笑った。
「相手に届けるための手紙じゃなくて、自分のために書くっていうか…改まったものを書くっていうのはメールと違って新鮮ですよ。特に、届けるつもりのない手紙なら、案外照れくさい事も書けますしね。」
寂しいのがまぎれるかもしれません、そうして、異国の手紙の書き方を教えてくれたのだ。レオリオは今、その改まった手紙に挑戦している。
「拝啓…くそっ、季節の挨拶はなしだ、なし。誕生日おめでとう。クラピカ…お前の誕生日にオレはこれを書いている。オレは…」
机の前の開け放した窓から柔らかな風がはいってくる。穏やかな春の午後だ。ふと、レオリオは顔をあげて考え込んだ。
「オレ、じゃなくて私、だな…メールじゃねぇし、あなた、といくか。ま、どーせクラピカに渡す事ぁねぇんだしな。」
こうなったら徹底的に改まってみるか、レオリオは気合いを入れなおして便せんに向かった。
『拝啓
クラピカさん、お元気ですか。私も元気です。あなたのお誕生日なので手紙を書きました。』
「……これじゃ阿呆だろう、オレ…」
レオリオはまたくしゃっと便せんを丸めてゴミ箱へ投げ入れた。
「やっぱ、らしくなさすぎんのもなぁ。」
ぼやきつつ、それでもレオリオは楽しそうに目を細める。
「オレらしく、しかも丁寧にな。」
再び、新しい便せんにペンを走らせた。
『拝啓
今日、久しぶりに丘の上の公園にいってきた。お前が帰ってくるといつも散歩に行くあの公園だ。いつのまにか、あちこち花が咲き始めていて、本当に綺麗だった。花が咲き始めると、お前の誕生日がくるのだな、と実感するよ。誕生日おめでとう。クラピカ。変わりはないだろうか…』
うわっ、らしくねぇ〜っ、レオリオはペンを握ったまま赤くなって呟いた。
たしかに改まってみると手紙のほうがこっぱずかしいセリフを並べられる。気を取り直してレオリオは続けた。
『お前は薬草に詳しいから、一緒にいるとよく草木の話をするだろう。そのせいか、オレは季節ごとの花や木にお前の姿を思い浮かべるようになったようだ。柄にもない、とお前は笑うかな。』
「んっとに柄じゃねぇよ、柄じゃ。」
ペンを走らせながらレオリオは一人ブツブツ呟いた。春の風が優しく頬をなでていく。
『公園の、海風のあたらないくぼ地に並木道があるのを覚えているか。葉っぱが柔らかくて美しいとお前が言った、あの並木だ。あの木々が今、枝一杯に花を咲かせている。薄ピンクの花で木々が覆われていて、そりゃあ見事だ。東の国からきた友人が名前を教えてくれた。桜というのだそうだ。彼の国の花で、花が咲くとその国の連中は皆、酒や食べ物を持ち寄って花の下でパーティをする習慣があるらしい。』
「なんだかんだ言ってもおめぇも花より団子のくちだよなぁ。」
子供のような顔で甘いものを頬張るクラピカを思い出して、レオリオはクスクス笑った。カッコつけてるくせにクラピカは甘いものに弱いのだ。
『確かに、浮かれるほど本当に美しい花だ。オレはしばらく見愡れていた。柔らかい花びらが風もないのに散ってくるのが楽しかったし、優しげな花の様はお前が笑ったみたいだったから。ぼうっとしているオレを見て、よほど桜を気に入ったのだと思ったらしい。いや、実際、気に入ったんだが、その友人が桜について、いろいろと話をしてくれた。それは桜を使った食べ物のことだったり、染め物や工芸品の図案のことだったり、お前であったら興味深くその話を聞いたかもしれないな。生憎、風流に縁のないオレでは今一つわからないことばかりだった。ただ、最後に聞いた桜の話が妙に気になった。彼の国では桜は愛されるが故、様々なイメージを重ねられてきたのだそうだ。それは、人を惑わす妖艶な魔性だったり、花の散る様から潔い死に様だったり、とにかく、咲き誇る花のあまりに見事な様子に人々は死のイメージを重ねてきたと言うのだ。』
レオリオはここまで一気に書くと、ぽつんと独りごちた。
「まったく、縁起でもねぇっての…」
『内心、オレはどきりとした。たった今までお前の面影を花の中に追っていたのに、死のイメージといわれて気持ちの良いはずがないだろう。いや、そうじゃない。オレには何故か、彼の言葉がお前の持つ何かに重なるような気がしてひやりとしたんだ。』
レオリオはそこまで書き終わると、眉間に皺をよせたまま窓の外に目をやった。
ぴちゅぴちゅと、遠くの空に鳥の声がする。少し煙ったような、優しい青空だ。レオリオの胸がつきんと痛んだ。
再びペンをとって書きはじめる。いつしかレオリオは手紙を書く事に夢中になっていた。
『お前には妙に潔いところがある。オレはそれが恐ろしい。お前は別に自分を粗末にしているわけでもないし、命への執着だってある。ハンターとして生き延びる能力が高いのは言うまでもないだろう。それなのに、オレはふと不安になるんだ。お前の潔癖さが、真直ぐさが、オレからいつかお前を奪うんじゃないかと。』

